このコラムは、小松義邦氏による、2025年10月12日のコラムです。※10月5日公開のコラムを改訂しました。▼
皆川家の討死者名簿について
2025年1月に、皆川家の家臣の名簿3点を、解説を入れて冊子として発行した。その後、2025年6月に『皆川広照、再起への道~幸嶋若狭大坂物語を読む』を作ったあと、2021年に私自身が復刻した近藤兼利 著の「皆川広照伝」の末尾の付録に、582名掲載の「皆川家臣討死者記録」を発見。それを加えて名簿4つとした改訂版を「皆川家臣帳」と名付けて、2025年9月に発行した。

「皆川家臣帳」2025年9月発行版での「今後の研究課題」について
その2025年9月発行の「皆川家臣帳」の「解題」に「晴天の霹靂」と書かざるを得ないほどに私が驚いたのは、「皆川家臣討死者記録」の最終頁に「元和元年五月六、七日大坂の陣」という項があって、そこに八十三名の名前があったことである。人数が多すぎるのである。
私は、解題の100頁に「なぜ『皆川家臣討死者記録』にこのような記述が残されていたのか、その意図を汲み取ることは編者(小松)にはできない。とはいえ、これはこれで、今後の研究課題とされるべきであろうと思う。」と書いた。
その後、考察を重ね、私としての結論を得たので、お伝えしたいと思う。形式としては、「皆川家臣帳」増刷の際に、最終項として追加するであろう形として、記載させていただく。
「大坂の陣の討死者八十三名」のこと
……
さて、最後に大変大きな命題が顔を出してきた。それは従来までの皆川氏関連書では窺えない「大坂夏の陣」での八十三名の討死者の名簿である。この八十三名の中には、本書78頁にある「皆川家臣討死帳」の大坂の陣討死者七名の内の、膝附大膳以外の六名の名もある。(膝附大膳については後述)
広照父子と共に大坂の陣へ参加した人数は、近藤兼利氏は三十四名、大森隆司氏は三十七名とそれぞれの著書にあるので、ここにきて八十三名の討死者があったという「討死者記録」が残されていたということは、筆者にとってはまさに「晴天の霹靂(急に起きる雷の大きな音)jという言葉そのままの衝撃であった。
有り得ない、からの考察
だが、これほどの討死者を出せるほどの兵力で広照らが参戦できたとはとても思えない。この「討死者記録」が前述の両氏の著書の「付録」として付けられていながら、両氏がこのことに一言も触れていないのも、同じ判断からかもしれない。
ではなぜ「皆川家臣討死者記録」にこのような記述が残されていたのか、この点について少し考えてみたいと思う。
この「記録」の書式の流れから見れば、ここに掲示された八十三名の名はどう見ても「討死者名」である。先述したように、名簿冒頭の「布施木平左衛門・今川民部・竹沢佐五郎(佐太・柴田下総・辺見団蔵・安生産内」の六名を見れば、本書78頁の「皆川家臣討死帳」の記載内容と同じであることから、「討死帳」として受け取らざるを得ない気になる。
名簿から抜けていた膝附大膳
なお、この「討死帳」にある膝附大膳の名が「討死者記録」に記されていないのは正しいことである。膝附大膳は、後年(日付未記載)「膝附大膳覚書」を残していて、その文の書き出しに
「先年慶長卯の年、大坂御陣の時、私は皆川志摩守隆庸様のお供をして、井伊掃部頭様の陣に加わり功名を挙げました。」(意訳)
とあるので、むしろ、前記「討死帳」に名があることが誤りなのでる。
ちなみに、「皆川家臣討死帳」の天正十二年の「川原田」の項に馬廻り膝附大膳の名があり、天正十六年の「草倉」の項には大目付膝附大膳亮(だいぜんのすけ)の名がある。
有り得ない、理由
さてそれはそれとして、大坂の陣での討死者が八十三人というのは有り得ないことであって、その理由は大きく分けて次のように二つある。
その―つは、これほどの人数の討死者を出す戦いとなれば、数百人規模の軍団で交戦して大敗した時ということになる。しかし、徳川の関連家臣と認められていない者たちの陣借り集団がそれほどの規模で参加できるわけがない、ということである。
二つ目は、ここに記された氏名を、五十音順に並べ換えてみると見えてくる。
元和元年五月六、七日 大坂の陣
安生産内 安生大膳 安生利左衛門
新井豊前守 新井丹後守 新井図書 新井助八郎
荒井重左衛門 荒井新左衛門
飯田但馬
池田重兵衛
石川太左衛門 石川左内
今川民部
氏家和泉守 氏家三太夫 氏家善次郎 氏家吉右衛門 氏家与四郎
氏家源之丞 氏家監物 氏家清七 氏家利兵衛 氏家清左衛門
大沢兵左衛門 大沢伝右衛門 大沢四郎衛門
大島新兵衛 大島市左衛門
小倉丹波守 小倉清兵衛
押山嘉右衛門
小曽戸惣左衛門 小曽戸三右衛門
小曽根僭濃
落合越前守 落合与惣左衛門 落合文右衛門 落合重助
柏倉豊前守 柏倉九左衛門 柏倉加左衛門 柏倉次左衛門
加藤新左衛門
小竹孫左衛門
佐熊淡路守
柴田下総
関口若狭守 関口善右衛門 関口清太郎
早乙女久助
高田主水 高田権兵衛
高林所左衛門
竹沢佐五郎
田城久左衛門
立川監物 立川吉之丞
田中久作 田中右衛門
中田四郎兵衛 中田九兵衛
仁田儀左衛門
新田内匠
日向野次右衛門
福田孫右衛門
布施木兵左衛門
辺見団蔵
巻島主水
松山肥後守 松山左次兵衛 松山長左衛門
松本伊賀守 松本四郎兵衛 松本平右衛門
森田伊豆守 森田長右衛門 森田三右衛門 森田清蔵 森田清左衛門
渡邊藤左衛門 渡邊久右衛門 渡邊隼人
単独名も多いが、何々の守という受領名を持つ者を頭にして三~八人もの同族が名を連ねている家が大半であり、これはあきらかに一族旗揚げ(挙兵)の姿である。これが、このまま大坂の陣での討死者となれば、下野皆川の地は大パニックに陥ってしまう。それは、領主としての皆川家が存在しない限り何の補償も出ないからである。
したがって、これはどう見ても有り得ないことであるといえる
結論 ―― その名簿は何か
以上のことから、この「大坂の陣」の部分に限っては「討死者記録」ではなく、「大坂夏の陣」への参加を希望して、武州(江戸)千住の広照父子の宿へ集まった(「皆川歴代記」)人の「交名帳(こうみょうちょう)」、または、事情で参加できなかった人たちの無念の思いのこもった「連判帳」ではないかと思われる。
※「交名帳」とは、「主旨に賛同する人々の名を連ねた文書。」(『戦国古文書用語辞典』)
それは、本書80頁の「大坂表供奉」(大阪の陣に参加した者の名簿)三十四名の内の前記討死者六名を除く他の者の名が一人も入っていないところからも推測されることである。
慶長十四年に家康の勘気を受けた広照に連座して浪々の身となり、多くの旧臣に助けられて再起への手がかりを掴みかけた隆庸と共にその身を挺して功名を挙げたいと願って、 はるばる下野から駆けつけた人々の、熱い思いのこもった連判状の写しであったと思いたい。
ここで再度名前を出すが、膝附家は皆川家の重臣で、同じ官途名の膝附大膳が、過去に二人も討死していることは先にも述べた。令和三年に県立栃木博物館で行なわれた「長沼氏から皆川氏へ」の展示会場の展示物に膝附家に関する書状の写しが六点あり、そのうちの「五十」に「皆川隆庸官途状写」があり、『図録』に付けられた「読み下し」は次のようになっている。
官途の事申し上げるに付き、すなわちこれを成し下さる者なり
慶長十五 霜月吉日 隆庸(花押影)
□□大膳亮
[解説]
皆川隆庸は、慶長十四年( 一六〇九)に父広照が徳川家康の勘気をこうむって所領を没収されたのに連座して没落した。これにともない、膝附常正も牢(浪)人を余儀なくされたものとみられるが、その後も隆庸への奉仕を怠らなかったため、その恩賞として大膳亮の官途を与えられた。大膳亮の実名は、膝附家系図では常正とされる。
このように、主家を失った者の再仕官の道は険しく、旧主を助け、再起への努力を続ける人たちの多い時代であった。このとき、費用不足などで戦旅を断念せざるを得なかった者たちの尽忠の思いをこめた名簿と、大坂の陣での討死者の名簿とが合わせて書き写されてきたものが、「討死者記録」であろう。
所感
私のたどり着いた結論が正解であるとするなら、旧主家のため、ひいては自分たちのためにと張り切って皆川を出て江戸の外れの千住の宿に集まってはみたものの、百人もの人数での陣借りは難しいという状況と、全員の戦費・旅費を自分たちでまかなうことができないという現実に直面し、さぞや辛いことだっただろう。
地元の声援を受けて出てきたけれど、資金がないという現実があり、協議した結果として主従合わせて三十六名のみが大坂への途につくことになり、別れの盃を交わすことことになる。そして、残留する者たちが、皆川の地へ帰るにあたり自分たちの志をせめてもの形にして残したいとの思いで、その席で名前を書き連ねた連判状を、広照に差し出したのだと思う。
その連判状が、その後も大切に伝えられ次々と書き写され、討死した六名の名とともに村方に広く伝えられ、どこかで一枚に書き継がれた際に「討死者記録」とされてしまったのだろう。
この一連の名簿の向こうに、千住での別れの宴の情景が見えるようで、胸が詰まる。思いのこもった連判状と受け止めて、この「皆川家臣討死者記録」を大切に残したいものである。
刊行情報
『皆川家臣帳』
2025年9月 改訂版発行
A5版
編集・解説執筆/小松義邦
発行/小松義邦
在庫あり 600円(郵送の場合はプラス送料210円)
詳しくは下記ページをご覧ください。
「皆川家臣帳」は皆川広照を筆頭とする皆川家の「家臣たち」の名前を後代に残します。2025年9月改訂版発行
◆皆川広照、再起への道~幸嶋若狭大坂物語を読む~ 800円
◆皆川家臣帳(改訂版として2025.9再販) 600円
◆口語 皆川歴代記(改訂版として2025.8再販) 800円
◆口語 別本 皆川正中録(2025.7再販) 1300円
◆復刻版 皆川広照伝 (残部僅少) 700円 ※皆川街づくり協議会発行冊子の取次販売
※郵送の場合、1冊につき送料210円です。
ご購入申し込み・お問い合わせはこちら
栃木市西方町の郷土史家。
研究対象/真名子の八百比丘尼伝説、皆川広照・皆川氏、西方町の歴史・西方氏ほか
――――――――――
栃木市編入前の西方町にて、町教育員会からの委嘱で1998年(H10年)に西方町郷土史研究会を発足し、史料集めや古文書解読に励む。2011年(H23年)発行の「西方町史」編さん時には一部の執筆を担当し、その後の町発行の「西方町の民俗」の編集も担当するなど、行政から信頼を寄せられる。研究成果を地元に残そうと、私家版として多数の冊子を発行し、地域の図書館への寄贈や、一部の書籍は地元小中学校の生徒に無償での配布なども実施。栃木市皆川町の「皆川地区街づくり協議会 歴史文化部会」からの委託を受けて「皆川広照伝」を復刻。郷土史を研究し、冊子を発行し続けている。










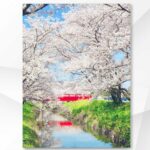













コメント